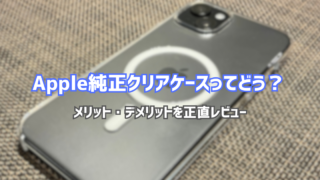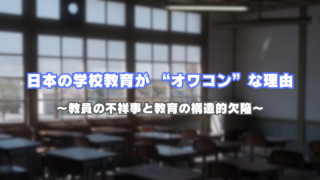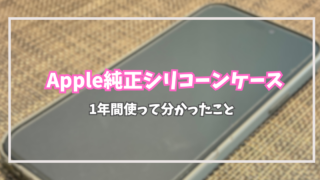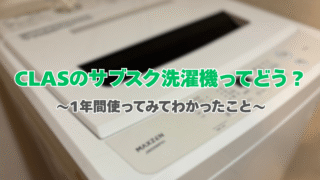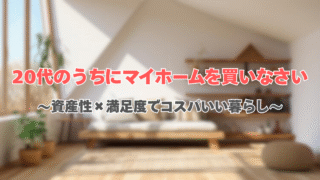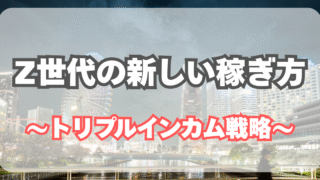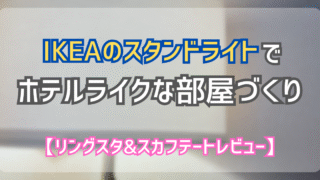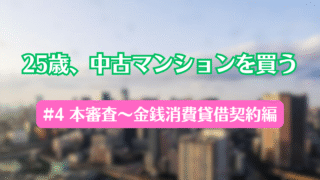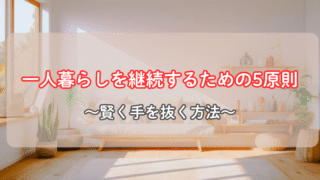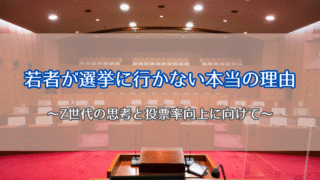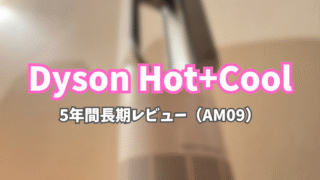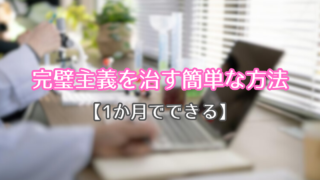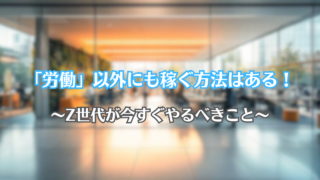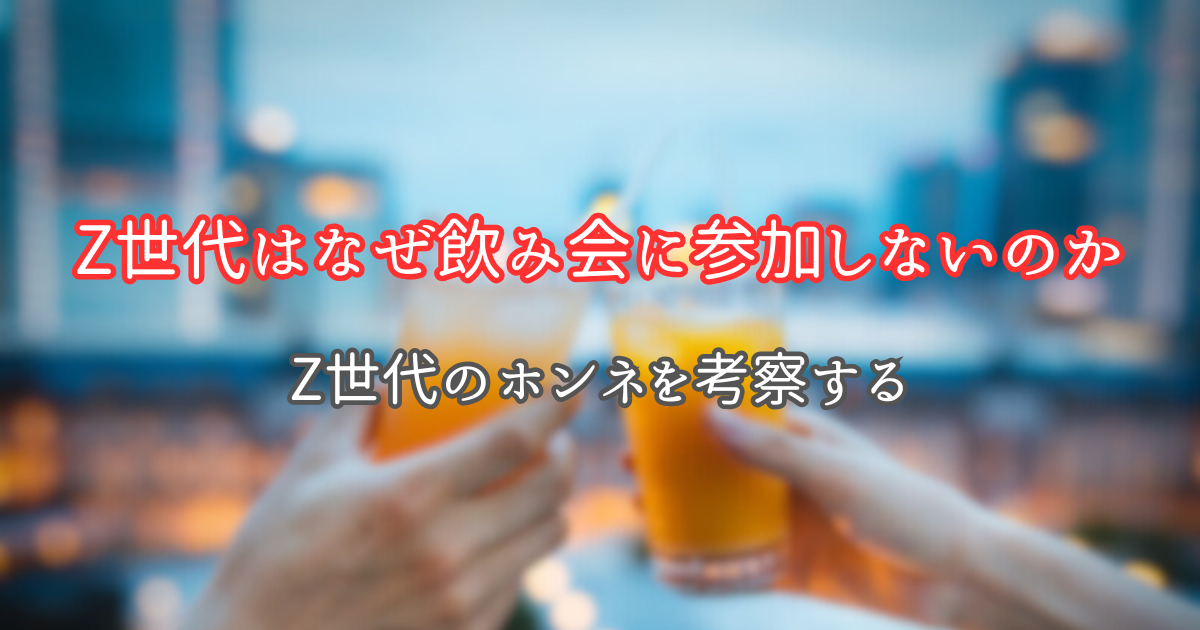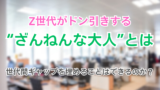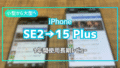「会社の飲み会に若手社員が参加しない」「Z世代との距離の縮め方がわからない」
かといって、何かを強制すれば”ハラスメント認定”される恐れも…。
こうしたことに頭を悩ませている上司も、少なくないはずだ。そこで本記事では、”Z世代特有の思考”をたどりつつ、Z世代と親世代の円滑なコミュニケーションの取り方について、考察してみたい。
Z世代と親世代のギャップ
「会社の飲み会は、若いうちは出席した方が良い。」「上司の誘いを断るべきではない。」
そんな考え方は、今の若手社員には通用しない。かつては出席するのが当然であった飲みの席だって、Z世代は断ることに躊躇がない。
親世代からすれば、今後の関係値に響くから参加しておきなさいと言いたくなるだろう。実際、飲みの席で親睦が深まり、業務の連携がとりやすくなったり、職場の雰囲気が向上するといったメリットも大きい。
だが、こうした”アドバイス”はZ世代には全く響かないどころか、嫌悪感さえ抱かれてしまう要因になる。
なぜ、こうしたギャップが生まれてしまうのだろうか。
紐解いていくと、「飲み会くらい我慢すればいいじゃないか」では済まされない、”本当の理由”が見えてきた。
Z世代が抱く親世代への「不信感」
Z世代の社会背景
そもそもZ世代とは、一般的に1990年代後半〜2000年代初頭に生まれた世代のことを指す。物心ついた頃から国内経済は停滞し、税金や社会保障費の負担は増え続ける一方。成長が著しい隣国を横目に、日本の国際的な地位は下がり続けていく…。
このような社会情勢において、幼少期からZ世代が感じていたのは「大人への不信感」だ。親世代が作り上げた”失政”が、自分たちのあらゆる可能性を潰していると考える。
実際、各種調査においても、諸外国と比較して「将来に希望を持てない」と回答する若者の割合は高い。
さらに、少子化により自分たちが圧倒的な「マイノリティ」であることが、若者たちを失望させる。高齢者中心の政策ばかりが展開されるシルバー民主主義に対し、為すすべがないことを悟ったZ世代には、「無気力」と「無関心」だけが残る。
かつてのような「今後給与は伸びていくし、大丈夫」「いずれなんとかなる」「大企業に入って将来安泰」といった、楽観的な思考を持つことはできなかったのだ。

将来の夢がない若者が増えているというね。
冷戦後の国際情勢しか知らないZ世代は、特段のイデオロギーを持ち合わせていないことも特徴とされる。かつての学生運動に代表される「自分自身で国家を変えることができる」「変えてやろう」という気概は、芽生える隙がなかったともいえよう。
言い換えれば、「諦め」こそが最大の抵抗だったのだ。
歪んだ教育と矛盾に満ちた社会
若者たちの不信感を募らせるのは、なにも政治的・経済的な面だけではない。自分たちが受けてきた教育への疑念、そして教育と社会の矛盾も大きな要因だ。
Z世代が受けてきた教育といえば、戦後日本における自由・平等・人権といった普遍的価値感に加え、マイノリティの尊重、道徳心、相手への思いやりといった、より洗練された人権意識をベースとした学問である。
-150x150.png)
社会の授業では基本的人権の歴史を学んだし、道徳の授業では「いじめは悪いこと」と教えられたね。
しかし、Z世代はここで多くの障壁にぶち当たる。それが、教育者自身による数々の「矛盾」だ。
一人ひとりの個性の尊重を教えつつ、集団行動を強制する教育者。理不尽な校則による不当な人権侵害。平等を教えつつ、生徒の主張を尊重せず意見を押し付けてくる教師。
こうした矛盾が累積していく中で、若者たちは大人への不信感を募らせ、次第に心を閉ざしていくこととなる。
Z世代に広がる”合理主義的”思考
大人は信用できない。そうであるならば、信じるべきは何か?
そうした中で、若者の心に刺さったのが”合理主義的”思考だ。
近年は、若者を中心に「コスパ」や「タイパ」という言葉が浸透し、かけた金額や時間に対してどれだけのリターンを得られるかといった「合理性」を求める思考が増えている。
こうした考え方が浸透するのは、インフルエンサーの発信を通じて、若者の間で共感を生んだからというのも一因だ。だが、元をたどれば、周囲の大人や社会に不信感を募らせたZ世代にとって、頼れる指針がない世の中を生き延びる”術”だったともいえる。
「理にかなった行動だけをする」「無駄な行動はしない」
こうした”合理主義的”価値観は、不合理な社会を目の当たりにしたZ世代の間で強い共感を呼び、いつしかメジャーな思考方法となったのだ。
若者が飲み会に参加しないワケ
ここまでみてきて、Z世代が会社の飲み会に参加しない理由がだんだんと見えてきたように思う。
それは、ただ単に「面倒だから」といった理由ではない。上司や周りの大人への不信感、時間や労力に対するパフォーマンスの悪さ、時間外にプライベートを犠牲にすることへの不合理さなど、本質はもっと根深いところあった。
- 上司・周囲の人間を信用していない
- 人間関係を重視していない
- 出世に興味がない・転職前提である
- 飲み会に出席する時間・労力・金銭に対する、パフォーマンスが悪い
- 時間外にプライベートを犠牲にすることへの不合理さ
Z世代の置かれた社会背景や教育環境による”人間不信”、それにより見出した”合理主義的”思考。その中で、会社の飲み会は、真っ先に「不合理」なものとして扱われたのである。
もちろん、飲み会に出席することで、仕事でも協力を得やすくなる側面はあるだろうし、若者の全員がこのように考えるわけではない。
だが、多くのZ世代にとっては「仕事のことは、仕事の時間内で、仕事の範疇で解決されるべき」問題であり、自らのプライベートを犠牲にして得るべき合理性は見出せないのである。
Z世代との関わり方
では、こうした考え方をもつZ世代とは、親睦を深めることは不可能なのだろうか?
答えは「否」だ。
確かに、彼らの思考の根底には、社会や上の世代に対する漠然とした不信感は存在する。
だが、それはあくまで一般論としてであり、自分の考え方を尊重してくれる人や価値観を共有できる人に対しては、素直に心を開く傾向にある。言い換えれば、親世代との関わりを一切拒絶しているわけではなく、本当に信頼できる人を見極めているだけに過ぎない。
だから、”ポイント”さえおさえることができれば、良い関係を築くことは難しくないのである。筆者の経験則も踏まえ、Z世代と信頼関係を構築するためのポイントをいくつか挙げてみた。
- 命令ではなく共感、同じ目線に立って話すこと
- 自分の考え方・従来の考え方ばかりを押し付けない
- 提案された意見・主張に対しては、合理的な理由でもって対応する
- 組織内の意見は民主的に決定する
- 親睦を深める活動は業務時間内に行う(時間外の活動は親しくなってから)
こうした取り組みを実践することができれば、自然と若者は自分にとって「安全圏」の人物・組織として認識するだろう。
Z世代とのギャップ解消に「社会」がすべきこと
では最後に、マクロな視点に話を移してみたい。ここまでは、Z世代と親世代の間で信頼関係が構築できる可能性について述べた。
だが、これはあくまで個別の対応方法について述べたものであり、「親世代への不信感」自体が解消されたわけではない。すなわち、彼らの社会背景や教育環境を踏まえれば、成長過程で染みついた根深い不信感は、簡単に取り払うことはできないのである。
もちろん、このまま分断を生み続けることは、社会にとってもマイナスの影響が大きいため、少しずつでも「矛盾」を解消する努力が必要だ。

ここからは、分断を解消するための案をいくつか提言していくよ。
まず、矛盾が社会・教育環境によって生み出されているのだとすれば、これらを改革する必要があるはずだ。
社会経済面では、若者の意見が反映され、現役世代が報われる社会を取り戻すことだ。努力が報われる正当な社会構造においては、大人や社会への不信感は弱まるだろう。
そして、教育面では、個を尊重する姿勢と民主主義の入門課程としての抜本的な改革が必要だろう。
個を尊重する姿勢とは、集団行動や不合理な校則など、時代錯誤な教育方針を撤廃することも一案だ。教育の質の向上のためには教員を削減し、有能な教員によるリモート授業の展開など、反発を生む施策も実行しなければならない。
また、現代の教育に欠けているのは、民主主義の入門課程としての自治教育だろう。
例えば、上から(教員・保護者など)の命令ではなく、生徒が自主的に統治を行い、サポート役として教員を割り当てるといった具合だ。他にも、校則を自分たちで民主的に決めること、教員を生徒が評価し待遇に反映させる仕組みづくりなど、いくつか手段は考えられる。
-150x150.png)
教育のあり方を根本から見直す時期に来ているのかも…?
「若者は飲み会になぜ行かないのか」という話からだいぶ広がった。
ただ、今のように親世代の「エゴ」ばかりを押し付けていれば、若者はますます不信感を抱き、分断が広がるのは避けられない。
これからを生きる世代に求められるのは、価値観の異なる者同士で理解し合い、相手を思いやる行動だろう。