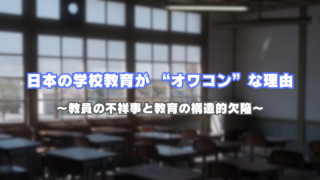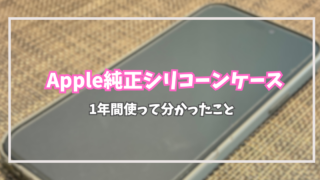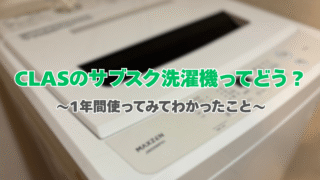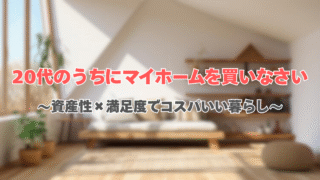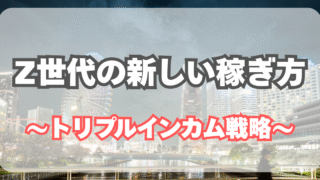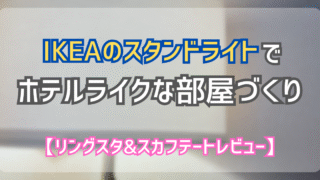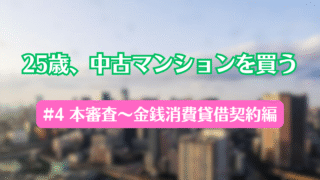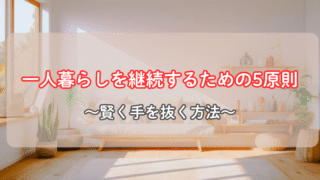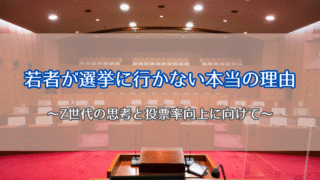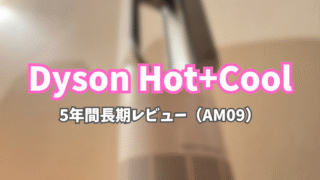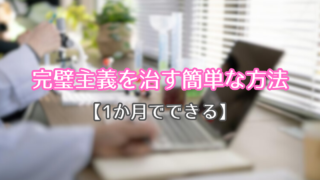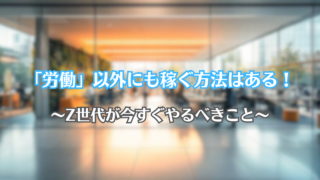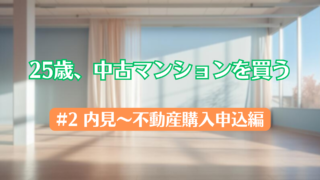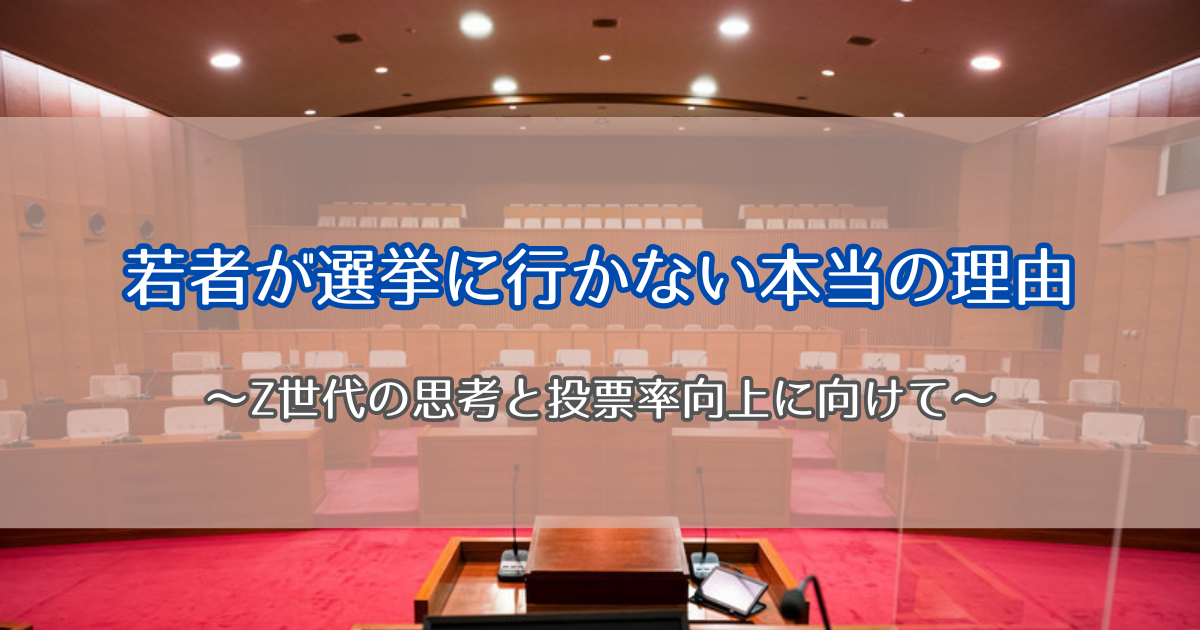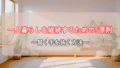Z世代の思考法について、同世代である筆者が、自身の経験を踏まえて考察する「Z世代のホンネ」シリーズ。
今回は「若者の選挙離れ」について取り上げたい。
若い世代(20〜30代)の投票率を見ると、近年は国政選挙でさえ35%程度にとどまっており、選挙への関心は薄い。
一体、なぜ若者は選挙へ行かなくなってしまったのだろうか。
本記事ではその原因を探りながら、改善策を考えていきたい。
若者が選挙に行かない理由
日本においては、憲法の下で「国民主権」が保障され、国民や住民の選挙によって代表者が選ばれる。
言論の自由は認められ、18歳以上の国民であれば等しく選挙権が与えられるなど、誰がみても明らかな民主主義国家だ。
にもかかわらず、主権者たる国民、特に未来を担うはずの若者が「選挙」という選択権を放棄するのはなぜか。
その背景を紐解いていくと、次のような原因が浮かび上がってきた。
- 日本経済の長期的な低迷と、少子高齢化
- 生死が切迫した状態にない
- 同調圧力の強い旧来的な教育環境
- 生き方・価値観の多様化
- SNSの発達によるコスパ・タイパの重視
もちろん、こうしたことが必ずしも全員に当てはまるわけではなく、個々の環境や性格に左右される部分は大きい。
ただ、ある程度の共通項から、上記のような”社会環境”や”環境にそぐわない制度”による「日本特有の複合的な要因」があるのではないかと考えられる。
それぞれ、詳細にみていきたい。
日本経済の長期的な低迷と、少子高齢化
日本経済の長期的な低迷が続き、少子高齢化が進行する、国の成長に希望が持てない社会。
まさに「かつての若者」と「今の若者」の育った環境において、決定的に違う点である。
特に1990年代後半〜2010年代前半に産まれたZ世代は、生まれた頃から「好景気」を経験したことがない。
「失われた30年」と言われるように、長期にわたって経済が上向かず、好転する見込みもない。
このような社会では、自身や国家に対する将来への期待感は薄く、投票への関心は下がる。
「誰がやっても同じだよな」という諦めが、若者の選挙離れを加速させる一因となっている。
生死が切迫した状態にない
経済が萎んでいく一方、生死に関わる危機的な状態に置かれていないことも、要因の一つだ。
例えば、日本に対して他国が武力行使を行ったり、内政に大きな混乱が発生すれば、自身や家族の生命・財産を守るためにも、関心は高まるはずだ。
同じ少子高齢化の課題を抱える韓国において若者の投票率が高いのは、敵対勢力に隣接し、すぐにでも戦争がはじまるかもしれないという「危機感」がある。
一方、日本においては、生きるか死ぬかの瀬戸際とまではいえず、国内経済もダラダラと緩やかに下降し続けている状況。
使命感や切迫感が生まれる「きっかけ」がないのが現状だろう。
同調圧力が強い旧来的な教育を受ける
さらに、こうした傾向を加速させているのが、日本特有の「同調圧力の強い教育方針」だ。
個性や自立心を伸ばす大事な時期に、日本の教育機関では「いかに周りから外れないか」が重視される。
自分の意思よりも周囲との同調を優先するよう求められ、本来の自分のあるべき姿・なりたい姿を見失ってしまう。
成長過程において個性を潰された若者にとって、今さら自身の長所を磨いて、将来への希望を見出そうといっても容易なことではない。
周囲との同調をさんざん叩き込まれた末「自らの意思で将来を選択しなさい」と言われても、選択できないのは至極当然ではないだろうか。

今後は一人ひとりの個性を伸ばす教育が必要だね。
一方、この点に関しては「かつては投票率が高かったじゃないか」という反論もありそうだ。
確かに、今以上に同調圧力の強かった過去の方が、若者の投票率が高かったのは事実である。
だが、それはあくまで経済や社会が「うまく回っていた」ときの話。
経済が成長せず、国際的にも立場が弱くなっていく社会において、”失敗した”日本式の教育は、若者の将来を悲観させるだけである。
生き方・価値観の多様化
同調圧力が強い教育を受けてきた反面、生き方や価値観の多様化が受け入れられつつある「移行期」でもある。
徐々にではあるものの、ハラスメントや少数者の権利に対する意識は高まってきた。
転職は当たり前になり、働き方は多様化した。
インターネットの登場により、多様な価値観を収集し発信できるようになった。
国際社会に遅れをとりつつも、先進的な価値観が流入し、若者の意識は変わりつつある。
そのような中で、価値観の変化に全く追いついていないのが「選挙制度」だ。
これだけインターネットが発達した社会にもかかわらず、ネット投票の議論すら進んでいない。
いまだに「電子メール」と「SNS」で選挙運動にかかる扱いが異なるなど、時代のニーズに合わない公職選挙法。
「制度そのもの」が時代にそぐわなくなり、結果として選挙への新規参入者を阻んでいる。

権力者にとっては、その方が都合が良いのかもしれないけれど…。
SNSの発達によるコスパ・タイパの重視
“デジタル・ネイティブ”である若者にとっては、幼い頃からパソコン・スマートフォンが身近にあった。
SNSで周囲と繋がり、瞬時に情報の取得や発信を行う若者にとって、「コスパ」や「タイパ」といった概念は特に重視される。
例えば、情報収集においては、数十秒〜1分程度のショート動画が流行し、要点が端的にまとめられたコンテンツを次々に収集していくのが主流だ。
また、X(Twitter)では、自分の興味関心のある分野にリコメンドされたニュースを、短文で効率よく収集するのが日常になった。
にもかかわらず、選挙においては各候補が複雑な公約を並べ、さらには自らが投票に行ったとしても”1票分”にしかならない。
「労力に対するパフォーマンスが悪い」と考える若者が増えているのは、仕方のないことなのかもしれない。
若者の投票率を上げる方法
では、若者の投票率を上げるためには、どのような対策が必要となるだろうか。
もちろん、若者自身が投票への意識を高めていくことは必要であるが、一方で「時代遅れの制度そのもの」を変えていくことも、責任ある民主主義国家の使命だ。
ここからは、若者の投票率を上げるために有効な制度について、検討してみたい。
インターネット投票の実施
デジタル化が進んだ現代において”必須”となるのは、インターネット投票の実施だ。
ネット投票が可能となれば、時間や場所にとらわれず投票が可能となり、投票に対するハードルは格段に下がる。
個人の認証についてはマイナンバーで行い、不正対策においてもブロックチェーンを活用することで、技術的に解決することは可能であろう。
ブロックチェーン技術による投票は、以下の記事も参考になる。
<参考記事>
朝日新聞社・START!「ブロックチェーンでついに「ネット選挙」が実現?その仕組みとは」
https://www.asahi.com/ads/start/articles/00283/
直接民主的な投票制度の導入
中・長期的には、今の間接民主制そのものを改善する余地があるかもしれない。
今の日本においては、地方自治や憲法改正など一部を除いて、原則として代表者を投票で選ぶ「間接民主制(代議制)」だ。
代議制というのは、国民一人ひとりの意見を反映することが困難だからこそ、代表者に決めてもらう、いわば「妥協策」としての制度だ。
しかし、インターネットを駆使すれば、国民自らが政策を立案・選択・決定するシステムを構築できる可能性がある。
国家レベルの課題や解決策を各自で考え、反映させることができれば、身近なテーマとして関心が高まるだろう。
クアドロティック・ボーティング
また、そもそも「1人1票」は妥当なのかという議論も存在する。
台湾のデジタル大臣オードリー・タン氏が紹介したことで有名になった「クアドロティック・ボーティング」という手法が参考になる。
この制度は、1人が複数候補に投票できるポイント制で、公平性を保ちつつ合理的な制度として注目された。
2019年に米・コロラド州の下院で実施されたこともある。
このように、柔軟な考え方で時代に即した選挙制度を提案し、実現させていく必要がある。

制度は形骸化しないように、常に見直す必要があるね!
まとめ
今回は、若者の「選挙離れ」について考察した。
若者自身の投票意識の向上は勿論のこと、日本特有の複合的な要因を踏まえ、社会構造や教育、選挙制度を根本から見直す時期にきている。
現役世代に希望が持てる社会へ、世代や党派を超えた議論が必要ではないだろうか。